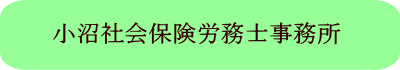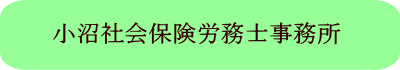|
| |
| 【年次有給休暇】 |
| |
| 雇い入れの日から起算して6箇月継続勤務をし、全労働日の8割以上勤務をした者については年次 |
| 有給休暇を付与する事を義務付けています。毎年、一定日数の年次有給休暇を与える事で労働者の |
| 心身の疲労を回復させ、労働力維持を図る事を目的としています。(労働基準法第39条) |
| |
| 年次有給休暇付与要件 |
 6箇月継続勤務(※1)した労働者 6箇月継続勤務(※1)した労働者 |
 所定労働日(全労働日)の8割以上出勤(※2)した労働者 所定労働日(全労働日)の8割以上出勤(※2)した労働者 |
| 8割以上出勤算定は下記の期間においては出勤したものとみなされます。 |
 業務上の傷病により休業した期間 業務上の傷病により休業した期間 |
 年次有給休暇を取得した日 年次有給休暇を取得した日 |
 産前産後の女性が労働基準法第65条の定めにより休業した期間 産前産後の女性が労働基準法第65条の定めにより休業した期間 |
 育児・介護休業法に基づく育児休業、介護休業を取得した期間 育児・介護休業法に基づく育児休業、介護休業を取得した期間 |
| |
| (※1)継続勤務の意味は出勤を意味するのではなく、「在籍期間」をさします。 |
| (※2)所定労働日出勤が8割未満の者に対しては休暇を与える事を要しません |
| ただし付与されない年があっても付与日数に関して(継続勤務)は追加されていく。 |
|
| |
| 年次有給休暇付与日数図 |
| 勤続年数 |
6箇月 |
1年
6箇月 |
2年
6箇月 |
3年
6箇月 |
4年
6箇月 |
5年
6箇月 |
6年
6箇月以上 |
| 付与日数 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
|
| |
| 年次有給休暇の比例付与について |
| 所定労働時間が通常の労働者と比べて短いパート労働者であっても付与要件が満たされれば年次 |
| 有給休暇を付与する事が労働基準法に定められています。 |
| |
 週所定労働時間が30時間未満のパートタイム労働者等のうち 週所定労働時間が30時間未満のパートタイム労働者等のうち |
 所定労働日数が4日以下のもの 所定労働日数が4日以下のもの |
 年間所定労働日数が216日以下のもの 年間所定労働日数が216日以下のもの |
| 下記の表のとおり年次有給休暇を比例付与する事となります。 |
| (※週所定労働時間が30時間以上のパートタイム労働者には通常の労働者と同様の年次有給休暇) |
|
| |
| 年次有給休暇比例付与日数図 |
| 所定労働日数 |
年間所定労働日数 |
6箇月 |
1年
6箇月 |
2年
6箇月 |
3年
6箇月 |
4年
6箇月 |
5年
6箇月 |
6年
6箇月以上 |
| 4日 |
169〜216日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
| 3日 |
121〜168日 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
| 2日 |
73 〜120日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
| 1日 |
48 〜72日 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
|
| |
| 労働者の時季指定権 |
| 使用者は労働者が請求する時季に有給休暇をあたえなければなりません。 |
| |
| 使用者の時季変更権 |
| 労働者が請求した時季に有給休暇を与える事が「正常な業務の運営を妨げる場合」には使用者は |
| 労働者が請求した時季を変更する事ができます。ただし単に忙しいから、人手不足だからと言う理由 |
| では通常、変更する事ができない事となっています。 |
| |
| 年次有給休暇に対して支払う賃金について |
| 労働者が年次有給休暇を取得した場合には就業規則、その他の定めるところにより、下記のいずれか |
| を支払う必要があります。 |
 平均賃金(原則、過去3箇月間の賃金総額をその期間の日数で割ったもの) 平均賃金(原則、過去3箇月間の賃金総額をその期間の日数で割ったもの) |
| ※賞与、臨時の賃金は除く |
 通常の賃金(有給休暇をとった日に通常通り出勤したものとみなし支払う賃金) 通常の賃金(有給休暇をとった日に通常通り出勤したものとみなし支払う賃金) |
 健康保険法による標準報酬日額(労使協定がある場合に限る) 健康保険法による標準報酬日額(労使協定がある場合に限る) |
|
| |
| 不利益取扱いの禁止 |
| 年次有給休暇を取得した労働者に対して、皆勤手当、賞与の算出に際して、欠勤に準じて取り扱う等 |
| の取扱は禁止されています。 |
| |
| 年次有給休暇繰越 |
| 使用しなかった年次有給休暇は、翌年度に繰り越さなければなりません。年次有給休暇の時効は2年 |
| となっています。(労働基準法第115条) |
| |
| 年次有給休暇の買い上げについて |
| 年次有給休暇は実際に休むことに意味がありますので、有給休暇を買い上げる事によって労働者に |
| 年次有給休暇を与えないことは労働基準法違反となってしまいます。ただし労働基準法を超えて有給 |
| を与えている場合においては、労使間で協約している日数分については買い上げしても差し支えない |
| 事となっています。 |
| |
| 年次有給休暇の効力について |
| 年次有給休暇は労働者が解雇、退職する場合はその効力が発生するまでの間に行使しないかぎり |
| 消滅します。 |
|
| |
| |
 |
| |
| |
|
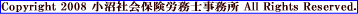 |