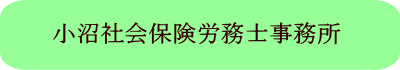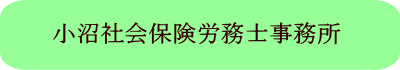|
|
| 【労働時間管理について】 |
| 近年、労働時間に関する問題が急増しており、未払残業、超過労働等様々な問題が大きな |
| 社会問題となっています。この背景には、使用者が労働時間を適切に管理していないケース |
| が多くあるといわれています。労働時間を管理する体制が全く整っていないケースや自己申告 |
| 制等により労働時間管理が曖昧になってしまっているケースは注意が必要となります。 |
| 労働基準法では使用者は労働者の始業、終業時刻を把握し管理する事が明確に定められて |
| おり、労働者の健康面からも労働安全衛生法により、労働者の健康保持のために必要な措置 |
| を講じなければならないと記されています。始業及び終業時間管理については使用者が自ら |
| 管理するか労働時間管理者が日々行うことが望ましいと言えます。とはいえ日々の業務におい |
| て、完全に労働時間を管理するのは困難です。次の手としてはタイムカードやICカード等により |
| 労働時間管理を行います。ここで注意しなければならないのはただ、タイムカード等を導入して |
| いればよいという訳にはいきません。そのシステムがしっかり機能しているかどうか?を定期的 |
| に確認する必要があるといえます。たとえば、始業時間よりも、2時間も3時間前にタイムカード |
| を通していたり、逆に終業時間を大幅に越えていたりした場合は注意しなければなりません。 |
| この事は現役の方に対しては言うまでもないのですが、退職された方からも問題となる場合が |
| 多いので特に注意が必要です。使用者が残業命令書等を作成しそれに対する報告書を記録と |
| して残す事も重要になってきます。客観的に確認できる記録等を残す事により適正な労働時間 |
| 管理ができるだけでなく労働者の健康を守る事ができます。 |
| |
| |
| 労働時間とは |
| 労働時間とは、休憩時間を除いた実労働時間をいいます。この実労働時間は必ずしも労働者 |
| が実際に作業等に従事している事を要しません。使用者からの指揮命令下にあり、いつでも指 |
| 示があれば対応できるよう待機している時間(いわゆる手待ち時間)も労働時間に含まれます。 |
| |
| 法定労働時間 |
 1日の法定労働時間 1日の法定労働時間 |
| 労働基準法では、1日の労働時間を8時間と定めています。(法32条) |
 1週間の法定労働時間 1週間の法定労働時間 |
| 労働基準法では、1週間の労働時間を40時間(※1特例対象事業除く)と定めています。(法32条) |
| |
| (※1)特例措置対象事業場(常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇(映画製作 |
| 除く)保健衛生業、接客娯楽業の事業場)の1週間の法定労働時間は44時間と定めら |
| れています。なお、1日の法定労働時間は8時間となっています。 |
| |
| (※)1週間(40時間)を実施する方法 |
| 変形労働時間制を採用せずに各週40時間を実施するには |
| ○完全週休2日制度を導入して(週5日)1日の労働時間を8時間以下にする |
| ○週休日を1日として1日の労働時間を6時間40分する |
| |
| |
| 対象となる労働者について |
| 管理・監督者(※1)及びみなし労働時間制(※2)が適用される労働者を除く全ての労働者 |
| (※1)管理・監督者とは、一般的には工場長、部長等労働条件の決定その他労務管理に |
| について経営者と一体的な立場である者となっており、役職名にとらわれず職務の |
| 内容から実体的に判断されます。 |
 労務管理に関し、経営者と一体的な立場にあること 労務管理に関し、経営者と一体的な立場にあること |
 出社・退社に関して厳格な制限を受けていないこと 出社・退社に関して厳格な制限を受けていないこと |
 賃金等、その立場にふさわしい待遇等がなされていること等 賃金等、その立場にふさわしい待遇等がなされていること等 |
| |
| (※2)みなし労働時間制とは |
 事業場外で労働する者であって、労働時間の算定が困難なもの 事業場外で労働する者であって、労働時間の算定が困難なもの |
 専門業務型裁量労働制が適用される者 専門業務型裁量労働制が適用される者 |
 企画業務型裁量労働制が適用される者 企画業務型裁量労働制が適用される者 |
| |
| (注)上記の管理監督、みなし労働時間制が適用される労働者についても健康の確保を |
| 図る必要があるため労働時間の管理を行う必要があります。 |
| |
| |
| 労働時間記録に関する書類の保存 |
| 労働時間記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、3年間(※1)保存する |
| 事となっています。具体的には、使用者自ら始業・終業時刻を記録したもの、タイムカード等の |
| 記録、残業命令書、報告書、労働者が自ら労働時間を記録した報告書などが該当します。 |
| (※1)3年間の起点日はそれらの書類ごとに最後に記載された日となります。 |
| |
| |
 |
| |
| |
|
| |
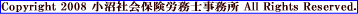 |